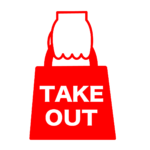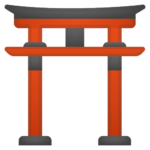名所・史跡をぶらり
高取周辺の見所を散歩がてらぶらりと紹介します。
高取焼味楽窯
始まりから現代に至るまで
高取焼の歴史は400年以上も続いており、その起源は興味深いものです。
朝鮮出兵の際、筑前国福岡藩主であった黒田長政が、朝鮮から陶工の八山(パルサン)を連れ帰り、鷹取山のふもとにある永満寺宅間に窯を開かせたのが最初の始まりと言われています。
高取焼は時代によって作風が異なります、初期の作風は「古高取」と呼ばれ、破調の美を象徴する豪放で大胆な作風が特徴でした。
二代藩主の時代には京都の茶人「小堀遠州」の指導を受け、古高取とは異なるわび・さびの優美さを焼き物に加えたと言われています。
その後、黒田藩の御用釜として保護され、1717年には現在の福岡市高取、より城に近い高取焼味楽窯が開かれました。
江戸時代に入ると、黒田の藩主は武功を立てる必要がなくなり、美術品の制作に注力するようになりました、その移転後の高取焼は、さらに洗練され、多くの茶道具の名品が生み出されるようになりました。
-1-1024x768.jpg)
写真:福岡観光コンシェルジュ
気品に満ち溢れた陶器
高取焼は、独特の技法である「掛け分け」や「面取り」、「流し掛け」と呼ばれる技法を持ち、陶器ながらも時期のような薄さと軽さが特徴です。
精繊な工程と、美しい釉薬、そして繊細できめ細やかな素材が魅力的です。
原料の土は2~3か月かけて丁寧に手作業で濾し、数か月寝かせます。
江戸時代から受け継がれる伝統技術で形作られ、鉄さび、藁灰、木灰、長石を原料とし、門外不出の独自の配合で生まれた7色の釉薬が使用され、約40時間の火入れを経て、迫力満点の大きな窯でゆっくりと焼かれます。
そうした手間暇かけた陶製品は、気品に満ちた魅力に溢れています。
紅葉八幡宮
深い歴史を刻む街の中心
紅葉八幡宮は、平安時代に陸奥国柴田郡からやってきた柴田氏が、産土神(その土地で生まれた人の守り神)の分霊を歓請し、祀った場所として起源を持つと言われています
1482年には、柴田繁信という柴田氏の子孫によってこの八幡宮が創建されました。
江戸時代には、福岡藩主である黒田家の守護神として重要視され、藩の安泰を祈る際にはまず紅葉八幡宮に参詣する習慣がありました。
藩主が社殿を建立する際、後陽成天皇の皇子である梶井宮慈胤法親王ご真筆の、金色に輝く神額を奉納し、大鳥居の前に家土を置き、交代で警護することが行われていたそうです。
そこから門前町が育ち、現在の西新、高取、百道、藤崎などが発展していきました。
大正2年には現在の紅葉山に遷座し、現代では「もみじに参れば万事吉」と言われ、紅葉山公園と共に、子供たちの遠足やスケッチ、花見、紅葉狩りなど、市民の憩いの場として親しまれています。

写真:福岡観光コンシェルジュ

もみじに参れば万事吉
紅葉八幡宮は、十二柱という祭神の多さから全国の大社に参拝したのと同じご利益があるとされており、応神天皇の母にして、安産子安の神として崇敬を集める神功皇后が祀られていることから、特に安産、厄除け、子供の守り神としての御神徳が篤く、安産祈願、お宮参り、七五三と大勢の参拝客で賑わっています。
また、秋には境内の木々が色づき、紅葉スポットとしても有名で、11月に行われるもみじ祭りでは、紅太鼓の奉納演奏、和傘灯り、ライトアップも行われ、美しい社殿と共に、訪れる参拝客を幻想的な世界へ包み込んでくれます。
写真:株式会社すこやか工房
元寇防塁跡
歴史的経緯
元寇とは、13世紀末にモンゴル帝国のフビライ・ハーン率いる元軍が、日本への侵攻を試みた出来事です。
元寇防塁は、この侵攻に備えて建設された防御施設で、この出来事は1274年と1281年の二度にわたって発生しました。
最初の侵攻では、元軍が九州に上陸しましたが、悪天候と日本側の激しい抵抗により退けられました。
その後の1281年の侵攻では、再び元軍が九州に攻め込みましたが、日本側の強固な防衛施設と激しい台風(風神風として知られる)の襲来により、元軍は壊滅しました。
元寇防塁は、このような進行に備えて、海岸沿いに築かれた頑強な防壁で、城や矢倉などで構成され、九州各地に築かれました。
元寇は日本における外敵の侵略として重要な歴史的出来事であり、その防塁は日本の防衛力を象徴するものとして、今日まで多くの人々に記録されています。
防塁の構造
土塁の構築:最も一般的な構築方法は、土を積み上げて塁を作ることでした。この土塁は海岸線に沿って築かれ、敵の上陸を阻止するための壁として機能しました。土塁は、地元の土や砂、石などで構築され、しばしば木材や茅草が利用されていました。
木造の防御施設:土塁の上には、木造の防御施設が築かれることもありました、これには矢倉(やぐら)や見張り台、防衛のための柵や壁が含まれます、これらの施設は敵の攻撃から防御するための拠点として機能しました。
地形を活かす:地形を利用して防塁を作ることも行われました、海岸線や山地など、自然の地形を活かして敵の侵入を難しくする工夫がされています。
元寇防塁は、当時の緊急事態に備え、迅速に築かれたため、その構造は比較的簡素なものが多かったと考えられています。
猿田彦神社
みちひらきの大神
猿田彦大神は、ニニギノミコトを高天原から葦原中国(日本列島)まで道案内をした国津神(古くからの土着神)の有力首長で、神話的な役割から、道を切り開くことや、旅路の指導者として、道開きの神として崇められています。
もともと街道の出入り口に祀られる道祖神(村の守り神)として伝えられてきたものですが、「猿」の字を冠する神と言う事から庚申(かのえさる)信仰と結びついたとされます。
以来60日ごとの庚申の日に祭りを行い、猿にちなまれ「災難が去る」「幸福が訪れる」という信仰を集めてきました、ここ猿田彦神社も唐津街道の出入り口に建立され、数百年の歴史を紡いでいます。

写真:wikipedia
庚申祭と猿面
猿田彦神社では、庚申祭(こうしんさい)が庚申(かのえさる)の日に行われます。
この祭りは中国から伝わった「六十干支(ろくじっかんし)」という暦をもとにしています。
それは十干と十二支を組み合わせたもので、60日ごとに年に6~7回、祭りが執り行われます。
庚申祭の日にのみ販売される猿面は、博多の人形職人が丹精込めて作り上げたもので、これを玄関に掛ける事で魔除けになると言われており、庚申祭の日には猿面を求める参拝客で長い行列ができます。2~3時間も待つこともありますが、それだけ多くの方々がこの猿面を求めているんですね。
福岡市では、家の玄関に猿面が何個も大量にかけられているのをあらゆるところで見かけることができます、猿面を収集する文化や趣味があるのかもしれません。
詳細な情報はこちらをご覧ください。
出典:
https://momijihachimangu.or.jp/
https://www.acros.or.jp/magazine/tradition08.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/promotion/mamechishiki/chishiki129.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%85%E8%91%89%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%AF%87%E9%98%B2%E5%A1%81
https://www.seinan-gu.ac.jp/introduction/facility/facility.html